| 氏名 | 役職 | 専門医等 |
|---|---|---|
 武田 義弘 (たけだ よしひろ) | 救急科(成人)主任部長 兼 循環器内科部長 | |
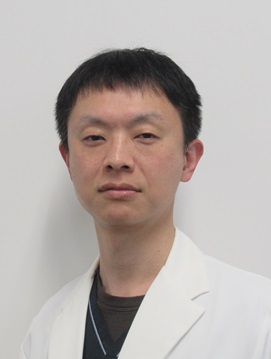 白數 明彦 (しらす あきひこ) | 救急科(小児)主任部長 兼 小児科部長 |
当院では、救急告示医療機関として365日24時間体制で二次救急診療を行っています。
日勤帯は救急を専門とする医師が小児科、産婦人科以外の救急患者の初期診療を行っており、小児科、産婦人科の救急患者さんについては、当該診療科の医師が診察を行っています。
日勤帯以外の時間帯は内科・外科系・小児科・産婦人科の医師が救急医療を行っています。救急科が初期診療を行ったあとは、必要に応じて専門科に引き継ぎ、切れ目なく診療が継続されるよう努めています。
救急では、個々の医療機関が一次救急・二次救急・三次救急のいずれかのグループに分けられます。
一次救急の医療機関は入院を要しない軽症のケース(初期救急あるいは一次救急)、三次救急は救命処置や集中医療が必要な重篤なケースの診療にあたります。
当院は、二次救急の位置づけとなっており、入院や手術、緊急処置などが必要な中等症以上の状態にある患者の皆様の診療を行うミッションを担っています。
また、重篤な患者の皆様の診療にあたる際には、状態の安定化を図りつつ、三次医療機関(救命救急センター)へ連携の上、搬送し、患者の皆様にとって必要な医療が迅速に受けられるよう努めています。
救急科で診療を行う患者の皆様の多くは、救急車により搬送されます。まず救急隊からホットライン(直通電話)があると、救急隊から病状などの情報収集を行います。
そして、救急車が到着するまでの間に、検査や輸液、人工呼吸などの準備を整えます。
また、必要に応じて院内の他のスタッフ(医師・看護師)へ応援要請を行い、十分な医療が行えるようにしています。
患者の皆様の到着時には、まず表情や様子などから、迅速に気道(A)・呼吸(B)・循環(C)・意識(D)・体温(E)などの状態を確認し、緊急処置が必要かどうか判断を行っています。
「酸素」と「身体の中の水」に不足がないかを判断し、酸素が不足している場合には酸素投与や人工呼吸を行い、身体の中の水が不足している場合には、輸液を行います。
またエコー(超音波)を用いて、循環に悪いところがないか(心臓がしっかり動いているか)を確認したり、循環不全の原因検索を行っています。
このようにして、気道・呼吸・循環の安定化を図り、また痛みを取り除くよう診療を進めています。
これら救急診療を行った上で、入院が必要な場合には、病状に適した診療科の医師へ引継ぎを行い、病状の回復を図っています。

救急車の車内です。患者さんが当院へ搬送されてきます。
*救急車の車内はあくまでイメージです。救急車により異なります。

救急隊から、患者情報を収集します。
患者さんが到着されるまでの間に、必要な処置の準備を行います。
二次救急の中では、平素のフレイル(加齢・認知症に伴う衰弱)程度が重度であるため、積極的治療を行うと、却って患者さんの生活の質を落とすのではないかという例も多く存在します。
このような場合は、フレイルの程度を見極める診察や問診・面接を詳細に行った上で、患者の皆様の意思を最大限に尊重し、敢えて延命や苦痛となる処置は控え、苦痛のみ除去する道を選ぶこともあります。
急変時の対応に備え、院内蘇生マニュアルの設定や除細動器の整備、アナフィラキシーへの対応、統一救急カートの整備を行いました。また、医療安全管理室との共同作業により、国際ガイドラインに準拠するウツタイン様式の心停止記録レジストリーも軌道に乗りはじめ、データの蓄積により、得られたデータから、院内救急システムの課題や対策を挙げています。日本救急医学会認定Immediate Cardiac LifeSupport:ICLS コースの開催は第53回まで実施し、非医療従事者を含む院内の全職員を対象とした簡易心肺蘇生講習会(PUSH コース)も並行して行っています。救急認定看護師会は看護局向けに精力的に、一次救命処置(BLS)研修会や、日本救急看護学会認定のファーストエイドコースを開催しています。これにより、院内における看護師のCPR や電気ショックによる蘇生成功事例も多数みられるようになってきました。心停止の認識からCPR 開始までの時間も有意に短縮しています。こういった院内の心停止データを収集して解析すること、正確なカルテ記載ができるようにシステムを整備したり、教育を行ったりするのも救急の仕事の一つです。
また、救急科に多くの患者の皆様が来院している場合に重症患者・緊急患者を素早く察知するために、日本臨床救急医学会が策定した緊急度判定支援システム(Japan Triage andAcuity Scale:JTAS)を導入して救急外来ナースのトリアージ能力を高めています。
| 来院方法 | 症例数 | うち入院数(率) |
|---|---|---|
| 救急搬送 | 3,067例 | 1,153(37.6%) |
| 自己来院 | 6,931例 | 867(12.5%) |
| 小計 | 9,998例 | 2,020(20.2%) |
| 来院方法 | 症例数 | うち入院数 |
|---|---|---|
| 救急搬送 | 1,533例 | 501(32.7%) |
| 自己来院 | 1,009例 | 655(64.9%) |
| 北河内夜間後送 | 254例 | 194(76.4%) |
| 小計 | 2,796例 | 1,350(48.3%) |
| 来院方法 | 症例数 | うち入院数 |
|---|---|---|
| 救急搬送 | 4,600例 | 1,654(36.0%) |
| 自己来院 | 7,940例 | 1,522(19.2%) |
| 北河内夜間後送 | 254例 | 194(76.4%) |
| 合計 | 12,794例 | 3,370(26.3%) |
どの専門医に紹介していいかわからない場合は当院救急科にご紹介ください。
円滑な対応ができるよう努めてまいります。